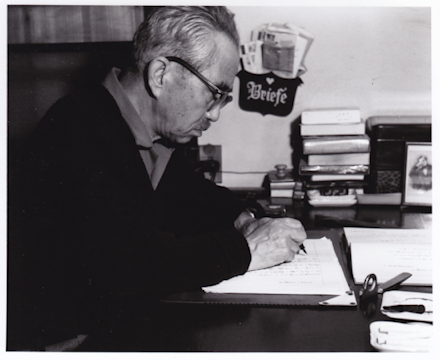明治二五年(1892年)1892年
一月三十一日旧東京市京橋区南小田原町に尾崎喜三郎の長男として出生。実母はいくばくもなく父と離婚し、代って原島氏しげ継母となる。この年東京府下荏原郡大井村字浜川の神山政五郎方に里子として送られる。旧東海道に面した海浜に海苔栽培とささやかな釣道具の店とを営む一家であり、ここでの実子の如き寵愛には今もなお懐かしい記憶がある。
明治二九年(満四歳)1896年
品川の天王様の祭の日、実父のかねてからの計画で東京の家へ誘拐される。実家は京橋区本港町にあって相当に手広い回漕問屋。隅田川を背後に鉄砲洲の河岸通りに面した古風な店がまえと数棟の倉庫。自家用の桟橋と外洋の航海にたえる二艘の三檣船。多勢の雇人と出入りの人々。急変した生活環境と家庭の空気とに幼い心は容易になじまず、ひたすら浜川の貧しい家と里親の温かいふところとにあこがれる。
明治三一年(六歳)1898年
新港町の築地小学校に入学。尋常一年の時の或る日、生みの母親という人が永の別れだと言って逢いに来て、下駄箱の処で私を抱きしめて涙にくれた。子供心にも美しい人だと思った。女の小使さんが泣き、何も分らない私も泣いた。
疳癖が強くて早熟で、本を読む事と自然を見る事とが好きで、小学校の諜程も首席で通した。
明治三七年(十二歳)1904年
小学校の旧制高等科二年を終って京華商業学校に入学。五年間の在学中成績は中位を上ったり下ったり、操行はおおむね乙、ただ国語、作文、英語、英作文、理科などには見るべきものがあった。父はこの頃すでに回漕業をやめて、地主・家主・株式投機等をやっていたが、我が子の学業のこの種の傾向を好まなかった。
明治四二年(十七歳)1909年
三月、京華卒業。母方の叔父の関係していた中井銀行に務める。小遣いは潤沢、親の眼をのがれる事もできたので文学雑誌を読みはじめ、当時流行の西欧文学者の作品を英訳の本で読みふける。たとえばモーパッサン、マーテルリンク、ゴルキー、ツルゲーネフ、アンドレイエフ、イプセンなどを。
明治四四年(十九歳)1911年
「文章世界」「スバル」等で初めて高村光太郎の名を知り、特にその文章「緑色の太陽」や「出さずにしまった手紙の一束」のような新鮮な芸術意欲と世俗への反逆精神とに貫かれたものに心酔して、彼の人間と風貌とを深く思慕した。英訳ではトルストイの「復活」から強い精神的ショックを受け、それ以来英語の本で手に入れ得る限り彼の作品を読み暮らした。この年銀行をやめて三省堂器械標本部に入社。小学時代からあこがれていた動植物の標本や理化学の用品に、日常自由に接する事のできる世界だった。文学と理科。この一見甚だ異なる二つの部門が私のうちで極めて自然に合流する気配を見せた。また前橋の高橋元吉と相識ったのもこの店での事である。そして彼のすすめで雑誌「白樺」を読みはじめ、文壇の新風や西欧の絵画に心をとらえられるようになった。
明治四五年(二十歳)1912年
徴兵検査に丙種で不合格。この年高村光太郎を本郷駒込のアトリエに初めて訪問し、文学志望の気持をうちあけて忠言をうける。引続いてトルストイに熱中、その伝記類も日本語のもの英語のものを手当り次第に買いこむ。中にロメイン・ローランドという人のトルストイ評伝があって、この本に最も深く心を打たれる。一方「白樺」もバックナンバーを揃えて読み、武者小路や志賀のものを特に愛した。
大正二年(二十一歳)1913年
三省堂器械標本部閉鎖のためやめる。七月に創刊された雑誌「生活」で高村光太郎の訳になる「ジャン・クリストフ」の一節を読んで感激し、居ても立ってもいられないような気持になる。そして早速ギルバート・キャナン英訳の「ジョーン・クリストファー」三巻を丸善から買って来て夢中になって読みはじめた。同時に自分の最も敬服しているトルストイ伝の著者ロメイン・ローランドが、すなわちこの偉大な小説「クリストフ」の作者ロマン・ロランその人である事を知って狂喜した。更にロンドンのダックウォース社発行の美術家伝記叢書で同じロランの「ミレー」を読み、別の粗悪な英訳書であのすばらしい「ベートーヴェン」も読んだ。この年も暮れるころ高田商会に入社。
大正三年(二十二歳)1914年
七月第一次世界大戦勃発。八月日本ドイツに向って宣戦。しかしこの人類史上最初の大事変に対して私には何等切実な反応がなかった。むしろ津田英学塾出身で務め先を同じくしている三歳年上の塚田隆子と恋愛におちいって、戦火をただ遠いヨーロッパの空のことと思っていた。その頃から武者小路実篤をまねて短かい小説様のものを幾つか書いていたが、この恋愛を書いたものを恐る恐る見てもらったのも同じ頃だったと思う。武者小路は「実感が出ている」と言ったが、取るにたらぬ愚作であった事は言うまでもない。また十月の或る日高村光太郎が務め先まで訪ねて来て、出たばかりの詩集『道程』を私に与えた。その本の扉にはペン書の自筆でルカ伝の中のキリストの言葉「無くて叶わぬものは只一つなり。マリアは善きかたを選びたり。こは彼より奪うべからざるものなり」の数行がフランス語で書いてあった。私の感激は言うまでもない。畏敬する二人の先輩、美しく賢い愛人、そしていよいよ募る文学への意欲。その間にも父との絶間のない軋轢が深刻の度を増し、母との仲も気まずく、常に悶々を重ねて生きてはいたが、ただ決して自棄にも無頼にも陥らなかった。トルストイやロランの名は言うも憚るが、高村、武者小路、或いは志賀直哉、私がそこに理想家の眼をもって倫理的人間像を見ているこの人々が、どんな場合にも妥協やごまかしを許さなかった。「……善きかたを選びたり。こは彼より奪うべからざるものなり」!
大正四年(二十三歳)1915年
秘密にしていた恋愛が発覚し、結婚もとより許されず、文学志望も断念を強制されると、自分が身をひくから思い止まってくれと言う愛人の言葉をしりぞけて、遂に私はみずから進んで父親に癈嫡を求めた。憤怒に燃えた父は騎鼓の勢いでおうむ返しに同意した。親戚や知人のとりなしなどは此の父と子とに全然効を奏さなかった。家を出ると務めもやめた。子供の頃からの自分名義の預金その他を与えられたので、向う二年間ぐらいの生活の保証はあった。愛人はそれ故になおさら苦しみ、私に秘して、自分は退くから父子の仲を元に戻してくれるようにと親戚の間を哀願して廻った。皆匙を投げていた。彼女の無私な心とその気品ある美貌とに動かされて奔走を試みた者もすげなく断られ、却って逆に叱責された。元より私もそういう事を望まなかった。漸くにしてかち得たこの自由の世界で永く求めて得られなかった人間の愛に生き、文学への志望を貫徹するというのが強い憧れでもあれば生き甲斐でもあった。私は癈嫡に関する法律上の手続きの済むのを待つ間、まだすっかりは落ちつかない心で浅草蔵前の愛人の家や(彼女はその先夫の子である幼い男の児と、年老いた日本画家で優しくて品位のある父親と、反対にはなはだ世俗的で肥満した継母との四人暮らしだった)、金の有るままに昔なじみの大磯・箱根・湯河原などの旅館を、転々とした。若い頃父の世話になったという大磯の旅館の主人に至っては、事柄をひどく簡単に考えて一人呑みこみで調停に出かけたところ、一言のもとに撥ねつけられて驚きあきれて帰って来た。思えば荒れすさぶような一年だった。しかし結局は私という一箇のエゴイストが、幾多の人の心を痛ましめ傷つけた独善と愚昧の嵐の一年だった。今はほとんど亡き数に入っているその人々の霊に、私は心から詑びなければならない……
大正五年(二十四歳)1916年
長与善郎氏の厚意でしばらくその赤坂の家に寄宿している間に、当然「白樺」の同人やその傍系の多くの人達と知るようになった。みんな若くて芸術意欲に燃え、息苦しいほどの空気が渦巻いていた。その中には「エゴ」という雑誌の中心人物、愛情に脆くて熱烈でくしゃくしゃになった千家元麿がいた。しだいにデューラー風な画風に移りつつあった傲岸不屈な岸田劉生もいた。私よりも一つくらい年下で、盛んにゴッホの手紙や後期印象派関係の本などを翻訳していた才人木村荘八もいた。椿貞雄がい、犬養健がい、近藤経一がい、道は違うがこの一群の空気を怜俐な澄んだ好奇の眼で見ていた学習院の生徒松方三郎もいた。ひとり高村光太郎は、離群癖というか党与の雰囲気を忌むというか、清涼な駒込のアトリエで粘土をつくね、のみを握り、静かにロダンの言葉の翻訳に専念していた。旋回する星雲系と遠く光る一つの星。私の心はこの間を微妙に往復した。そして或る日ロマン・ロランの音楽評論集『今日の音楽家』の新刊の英訳書を手に入れるや、渇いた者が泉に出逢ったようにこれに取りついて翻訳を始めた。ベルリオーズ、ワーグナー、フーゴー・ヴォルフ。「白樺」の人達には稍縁遠く、私には極めて親しく懐かしいロランの世界と音楽とが其処にあった。私の翻訳は直ちに採り上げられて「白樺」へ連載された。
そして早くも十二月には四〇〇頁(思地孝四郎装頓)の本になって麹町の洛陽堂から出版され、記念として長与善郎氏に献ぜられた。これが私の最初の本だった。そして私と喜びを共にして熱い涙の中にその一冊を抱きしめた愛人隆子の最初にして最後に見た私自身の本だった。
大正六年(二十五歳)1917年
悲恋はつづいたが私は持金をほとんど使い果たした。それで再び職を求めなければならなかった。務めた先は日本橋の或る化学薬品会社で、仕事は帳簿係だった。或る時築地の副社長の邸へ行ったら、それは曽て両親と共に私の住んでいた家で、父が当時の市村羽左衛門に売り、副社長がその俳優から譲りうけたものだった。その故か私は比較的優遇され、仕事そのものも楽だったので文章を書いたり翻訳をしたりする余暇が十分にあった。私はロランの評論を通じてベルリオーズを知り、この非凡な音楽家を気質的にも熱愛していたので、長与氏の家を去って新富町の下宿へ移ると直ちにその『自伝と書翰』という英訳本の翻訳にとりかかった。そしてそれが「ベルリオの手記」という題で「白樺」に連載された。(当時はまだ Berlioz の発音がはっきりせず、高村氏と相談の上でベルリオと治定していた)。隆子とはほとんど毎日のように会っていた。それぞれの務めの帰りに会ったり、彼女の方から私の下宿へ来たりした。しかし彼女の継母の手前を憚って、その浅草の家へは余り訪ねて行かなかった。一緒に二時間ぐらいを暮らして何処かで茶を飲んだり、たまには晩飯を食ったりしながら「ジャン・クリストフ」の、特にその心打たれる「アントワネット」や、翻訳中のベルリオーズを読んだりした。そのベルリオーズがまた悲恋の大家でもあれば告白者でもあったのだ! 私たちは私自身が満二十五歳になるのを待っていた。二十五歳になれば自由結婚ができたからである。二人の関係は夫婦と姉弟とのそれだった。淡い愁えの影を宿した恋の顔に手をもって触れる時、この美しい妻は同時に献身の姉でもあった。
大正七年(二十六歳)1918年
金の上で無理をせずにもっと自然に手軽く会うために、私は彼女の探し当てた浅草厩橋附近の貸間へ移った。蔵前の家とは目と鼻ほどの近くなので、彼女は近所への買物のたびに始終立ちよった。務めの時のでないその家庭での女姿が私には珍らしくも恋しくもあった。しかしそんな事だけに夢中になっていたわけではなく、一方では近くに住んでいた或るフランス語の教師からフランス語を習う事もはじめた。ロランやベルリオーズや又その頃高村氏から奨められたヴェルアーランの詩を、すべて原文で読みたいためだった。語学にはいささか恵まれた力があったせいか進歩は早かった。天文学にも興味を持って先ず星座の知識を得る事から始めた。橋の上や駒形の河岸から星図と首っぴきで春や夏の夜空の星を眺めた。或る時、その下宿へ女のほうの里親が訪ねて来た。実家を出てから初めての再会だった。私を自分の乳で育てて我が子のように愛してくれた老いたる里親は、父も最近脳溢血で倒れてから気が弱くなり、初めの頃の怒りも憎しみも漸く解けて来たようだから、できるならばこれをしおに和解の道を講じて元の鞘に納まるようにしたらどうかと私を説いた。しかし折から来合せた隆子を一目見ると、どうか此の子を宜しくお願いしますと頭を下げて帰って行った。そして電車道まで送りに出た私に銀貨ばかりの重い金包みを渡しながら、あんな別嬪ではお前さんとしてもと言いさして品川行の電車に乗った。志賀直哉氏から親切な長い返事の手紙を貰ったのもそれから少し後の事だった。私はこれも父と子の背離をテーマとしたその「和解」を読んで深く心を勤かされ、彼も薄々は知っている私の場合を詳しく書いてその忠言を求めたのだった。と言うのは、その頃日本築城術研究の権威であった某博士から妻として隆子所望の話がしきりで、継母がそれに乗気になり、隆子を強制して私と別れさせようとしていたからである。自分という者がある以上父と子の和解は不可能だと信じていた彼女は、この恋愛を断念し、一身を犠牲にして進まぬ緑談を受け入れるべきではないかという、真に苦しい心境に悩んでいた。彼女は高村氏にもその衷情を訴えたらしい。高村氏は、それは二人の愛の深さによる事で、もしも互いがその愛によって強いならば、断然世俗の感情をしりぞけて初一念を貫くがいいと言ったという。一方私のはそういう真剣な苦悩でも迷いでもなかった。すべてを既成の事実として父に認めさせた上での和解を前提とした、甚だ虫のいい忠言の所望だった。それに対する志賀氏の返事は長い懇切な手紙だったが、要するに、同じ父子の不和と和解ではあっても人それぞれによって違う。自分のはあのようにして極く自然に成立した。君の場合にも無理があってはいけない。運命のおのずから割れる時を待つべきであろう。そういう慰めと警告との返事だった。あの志賀さんだ。禅機によっては本当の平手打ちをもくだす志賀さんからの返事だ。私はその警告に対してみずから恥じ、おのれの虫のよさを唇を噛んで悔いた。
大正八年(二十七歳)1919年
第一次世界大戦は前年の十一月に終結したが、その前後から蔓延をはじめたスペイン風という悪性のインフルエンザが我が国でも猛威をふるって、東京でも続々と人が斃れた。一月隆子もこれに襲われた。初めの内は単なる感冒ぐらいに思っていたのが次第に重くなり、病苦と心の悩みとを抱いて自宅で床につくようになった。妹の夫である若い医師が手をつくしたが甲斐がなかった。すでに死の影が暗くたちこめていた。私は元より病床につききりだった。彼女は近い死を覚悟しながら、この五年間の愛に感謝し、自分の至らぬ故だったと言って詫び、私の将来の幸福と立派な仕事とを祈った。時々熱に浮かされて口にするうわごとは「お父さん」だった。彼女を慈み、継母から彼女をかばい、その前夫のための苦しみや私のための悩みを哀れに思いつづけながら、つい一年前にこの世を去った優しい父親を呼ぶ声だった。二月の四日、ついに危篤の時が来た。妹夫婦のすすめにさすがの母親も今は折れて、隆子と私とは幽明の界で結婚の杯を取りかわした。そして二月五日の早暁、むせび泣く妹、母親、先夫の子供にとり縋られ、義弟の医師に脈をとられ、その額に私の唇をうけたまま瞑目した。
Mea culpa, Mea culpa! 一切は私の罪だった!
愛人の死によって心に大きな空洞を感じた私は、会社もやめ、生活にも規律を失って、虚脱の状態で毎日を暮らした。それでも「白樺」の十周年記念号に「或る女の死」という戯曲めいた物を書き、その記念講演会で感傷的な講演もした。しきりに酒を飲みに出かけ、レコードで初めて聴くベルリオーズやビゼーに涙を流し、時々高村氏を訪ねるほかは人とも会わず、心に荒涼を抱いて歩きまわった。そしてこの年の十二月、母校の世話で朝鮮銀行に入社、外国為替係見習という名義で朝鮮京城の本店に赴任した。
大正九年(二十八歳)1920年
優秀な行員が揃い、学閥や縁故でぎっちり固められているこの国策的な大銀行は、とうてい私などの容れられる世界ではなかった。外国為替というものも初めてだったが、ヴェテラン揃いの中で仕事らしい仕事も与えられなかった。それやこれやで厭気がさして勤めも怠るようになり、ついに病気を名目に退社してその夏東京へ帰って来た。この京城で得たものといえば、数人の朝鮮人の友達と、日本の統治に対する彼等の内密な不平や憤懣への認識と、この半島の古都やその周辺の田園美を愛と同情との眼で見たことだった。それに李王博物館で働いていた金沢生れの木村泰雄という若い画家があった。この男とは意気が投合して孤独の中にも芸術上の楽しい時間を持つことができた。東京へ帰るや本郷の西片町に下宿を求め、高村氏とも頻繁に会って一緒にたびたび飲み食いにも出かけ、ベートーヴェンやベルリオーズの音楽にも感銘を共にし、彼の感化でヴェルアーランの詩を真剣になって読み、自分でも詩を書きはじめ、その推挙で牛込の叢文閣からベルリオーズの『自伝と書翰』という翻訳書を出すことができ、また伴われて荏原郡平塚村字下蛇窪の静かな田舎に水野葉舟氏を初めてたずねた。そしてここで初めて氏の長女で当時十五歳の実子(みつこ)という娘を見た。
大正八年、大正九年のこの二年間、ともすれば自暴自棄に陥りかねない私を、常にこまかな温かい心づかいで兄のようにみとってくれた高村氏は、まことに救いの大天使であった。
大正十年(二十九歳)1921年
芝の玄文社詩歌部から長谷川己之吉氏の手で創刊された詩の雑誌「詩聖」に、同氏のすすめで詩を寄せはじめ、ほとんど毎月自作と雑筆とが載るようになる。ここで大藤治郎、野口米次郎、田中冬二、中野秀人らを知る。また高村氏のアトリエで外国語学校イタリア語科の学生で彫刻家志望の若い高田博厚と相知り、以後ずっと親交を結ぶ。詩人井上康文氏とも知って、その主宰する詩雑誌「新詩人」にも詩を寄せる。印税や稿料など収入が少しはあって生活のメドがつく。十二月、水野氏一家への親しみと平塚村下蛇窪の静かな田園風景とに引かれて、彼等の邸に近い所に一軒の小さな家を借りて移り住む。現在の東京急行大井線の戸越公園駅に近いあたりである。
大正十一年(三十歳)1922年
国電大井町の駅から西へ十数町、竹林と屋敷林と灌漑用水の流れとの間に大小の農家の散在する田舎、遠く洗足・五反田・池上・馬込の奥まで、朝露に濡れ夕日にまみれて楽しい静かな散策のできる田園。私に詩がぞくぞくと生れ、文章が書け、「一行として書かざる日無し」のモットーが真に自分のために有るような気がした。引続いてヴェルアーランやホイットマンの詩を読み、ヘンリー・ソローの「ワルデン」と「日記」に傾倒し、高村・高田の両氏ともしばしば会いもちろん水野氏の家とは家族中の一人のように親しくした。
五月に玄文社詩歌部から最初の詩集『空と樹木』が出た。四六版上製箱入りで二四八頁、薄水色の表紙に高田自筆のフランス語の題を金箔で捺し、彼の作になる私の首のブロンズ像の写真を口絵にえらび、更に彼の愛妻を描いたデッサン一枚を挿画にした。詩壇での批評は賞讃するもの、こきおろすもの、いろいろだった。私はこの最初の詩集を敬愛する高村光太郎と千家元麿とに献じた。また英文で書いた手紙を添えてスイスのロマン・ロランにも一冊送った。すると七月の或る日、水色の封筒に小鳥の抜毛のような特徴のある文字で、端麗でしかも雄勁に書かれたロマン・ロランからの返書が来た。私は狂喜した。しかしこんな書体に出会うのは初めての事なのですっかりは読めなかった。東京へ出かけて高村氏に見せてもはっきりは解らず、神田一ッ橋の三才社(当時のフランス書専門の店)へ行って、なじみの老主人に見てもらった。夜だったが店の中のあかりが暗いので、主人は外へ出て度の強い眼鏡を額の上に押し上げながら、ガス燈の光で判読してくれた。手紙の中のその個所はこうだった——
「私の作品が日本で君たちのような読者や友を見出した事を嬉しく思います。それが世界の到るところで迫害をうけている人間の自由を擁護することに役立ちますように! また君たち極東の民族とわれわれ西欧の民族とに、精神的な友愛の関係をつくり出しますように! 私自身としては、もう久しい以前から、精神に国境というものを認めずにいます。私たち自身の個性をいささかも否定することなしに、否むしろ個性を高めながら、人類の大交響曲を作り出すことに努めようではありませんか……」
脳溢血のおそれのある首の太い赤ら顔の老主人は、私の顔をじっと見ながら、「尾崎さん、あなたはすばらしい人から大変な手紙を貰いましたね」と言った。私はその首玉へかじりつきたかった!
大正十二年(三十一歳)1923年
詩作もその発表も、翻訳の仕事もすべて前年と変りなく、実子との親近も深まってついに相愛の間柄になった。神田の書肆仏蘭西書院からベルリオーズの『ベートーヴェンの交響楽の批判的研究』を出す。しかし其の後間もない神田の大火で、その在庫品は大半焼けた。
九月一日正午にいわゆる関東大震災。自宅にも水野氏の家にも多少の被害はあったが、遠く東京の空にそびえ立つ大火災の煙柱を見ると急に矢も楯もたまらなくなり。交通機関のすべてとだえた戦場のような混乱の中を、京橋区新川の、今では親子の縁もない元の我が家へと数里の道を駆けつけた。風の便りに半身不随になっているという父親への骨肉の情がそうさせたのだろうか、或いはその人との感情の深い裂け目が、私のほうだけはもうとうに埋まってしまったと思い馴れているせいだったろうか、ともかく一気にたどりついて、まず我が家の近くの叔父の家へ行った。すると叔父は私の顔を見るなりほとんど怒鳴りつけるように、「来たのか、そりゃよかった!すぐ家へ行ってやれ!こうなっては出入りの者も何も来やしない。家はおやじとおっかさんと女中達だけだ。急いで行け!」と追い立てた。酒問屋の倉庫の立ちならぶ新川の河岸通りにはもう人影もなく、土砂まじりの風ばかりがごうごうと吹き渡っていた。幾年久しい我が家へ飛びこむと女中を督励して手廻り品を風呂敷包みにさせていた母が、「おとっつぁんは屋根の上だよ!飛火があぶないからずれた瓦を直すんだって言っているけど、それどころの騒ぎか、すぐ逃げるんですと言って下ろして来ておくれ!」と叫んだ。屋根の上、強風の中に老いた父はしゃがんでいた。そして私を見るとにっこり笑って、「来たか。手伝ってくれ」と静かに言った。この瞬間七年の背離、七年の不孝の感は吹っ飛んだ。私は彼の気の済むように手早く瓦を並べ直し、ほとんど抱くようにして下へおろした。もう大火は波のように蠣殼町、茅場町、箱崎町へ押しよせていた。火の粉が吹雪のように渦巻いて空を流れていた。私は活路として浜御殿か丸ノ内をすすめた。父は母と二人の女中に附添われて強風の下をのがれて行った。私はそれでも後へ残って、別れ際に父が言い残して行ったとおり、唐草の大風呂敷に包まれた客用の夜具布団を三組、息をはずませながら河岸との間を十度も往復して荷船の底へほうりこんだ。それから逃げた。もう背後はまったくの火の海、火の長壁だった。行く先々は風の吹きまく死の町だった。日本橋の大通りから丸ノ内をさして走っている途中、八丁堀で往来に倒れている一人の娘にぶつかった。その十八九になる重たい娘を引っかかえて一町か二町は走ったが、ついに力尽きて可哀そうだが置いて逃げた。楓川の運河に懸かった橋は、どの橋も家財を積んだまま置き捨てられた荷車にせかれて、中にはもう火焔に包まれているのもあった。私は火の嵐の中を渡れそうな橋を探して駆けずり廻った。最後に思いきって飛びこんで向う岸へ泳ぎついた。その時水中の杭に片膝を強く打ちつけた。京橋際の南伝馬町の角まで来ると、丸ノ内への鍛冶橋通りは避難の群集でぎっしりだった。その密集団にもまれながら、僅か三町ほどのところを一時間もかかってやっと鍛冶橋を渡り、ここもまた人で一杯の東京市庁の救護所へ倒れこんだ。半日余りの奔走に疲れ果て、あまつさえ片膝にかなりな打撲傷を負っていた。そして応急の手当をうけて、庭の片隅でぐっすり眠ってから、真夜中の道を青山・渋谷、目黒・五反田と市内電車や国電の線路を歩いて、翌日の夜明けにやっと蛇窪の我が家へついた。
要するに、この事あって以来急転直下、父親と私との間に和解が成り、そのうえ水野実子と結婚したいという希望もすらすらと受けいれられた。そして私や水野氏の知友である江渡幸三郎氏の家の近く、東京府豊多摩郡高井戸村大字上高井戸の畑地の中に一戸を新築して、そこに新夫婦で別居するがいいという事になった。王川上水を窓のむこうに、井ノ頭用水を背に、居ながらにして遠く富士や丹沢の山々を見ることのできる洋風二間の家と二反歩の畑地。来たるべき年の春の結婚を待ちながら、その新築の晴れやかな家で私は独身最後のクリスマスを祝った。
大正一三年〜昭和三年(三十二歳〜三十六歳)1924年〜1928年
十三年三月水野実子(十九歳)と結婚。文学の仕事と畠仕事に専念する高井戸時代の生活がはじまった、畠仕事とは言っても二人とも全くのしろうとだったから、何を作るにしても一々江渡氏の家の人達や近所の農家の指導にまった事は言うまでもない。私たちは怪しげな乎つき腰つきで鍬を動かし、肥料桶を運んだ。一個の桶を二人で担うのだった。そして百姓なみに旱天には雨を祈り、虫害を憂え、雀を追った。輪作に間作に、私たちの作った主なものは麦、大根、甘藷、里芋、白菜、馬鈴薯、胡瓜、葱などだった。それぞれの季節の収穫は、これを粉にしたり、漬物にしたり、乾燥したりして、貯蔵のできる物はすべて貯蔵した。さまざまの花も作った。これは奨められて切り花にして売ってもらった。鶏も白色レグホーンを飼った。その卵は食膳を賑わした。ほとんど収入にもならない詩を書き、幾らかは生活の足しになる散文や翻訳の仕事をしながらの自給自足の生活だったから、毎日同じような物が食卓にならぶ事が多かった。もちろん何かをしおに特別のメニューを持つ日も稀ではなかった。それにしても松沢の駅へ十町、甲州街道の雑貨屋へ五町、煙草屋へ七町、肉屋と魚屋へは十町の道のりがあった。
多くの、実に多くの友人の来遊があった。高田博厚、片山敏彦、上田秋夫のような連中は荻窪や西荻窪に住んでいて近くもあったので、頻繁に訪ねても来れば訪ねても行った。高村氏も四五回来た。一度は智恵子さん同伴だった。中野秀人も菊岡久利もたびたび来た。一々名を挙げれば切りは無いが、更科源蔵と真壁仁との名は書いて置きたい。みんな若くて燃えていて、それぞれの人が固有の夢と信念とを育んでいた。(今、三十年の歳月をけみして、彼等はそれぞれ曽ての夢を実現し、その信念の大地に立っている)武蔵野高井戸の田舎の小屋に談論は風発し、ヴィクターの小函からベートーヴェン、バッハ、ベルリオーズらの音楽が流れた。二人の女、新妻実子とその妹とは台所でくるくる舞だった。
十四年六月には長女栄子が生まれ、昭和二年七月には長男朗馬雄(ろまお)が生まれた。この長男の名はロマン・ロランのロマンをとって附けた名だが、翌年の三月流行性感冒で父に先だった。異常に澄んだ限を持った愛らしい子で、特に若い母親の掌中の玉だった。言わば名附親のロマン・ロランはこの子の死の知らせをうけとると、親たちを感涙にむせばしめずには置かないような切々たる同情の手紙をくれた。
十五年の五月にはフランスの詩人シャルル・ヴィルドラック夫妻が来日して、この高井戸をも訪れた。私たち高村・高田・片山・上田・田内静三、今井武夫、吉田泰司、尾崎らは、それより早くロマン・ロランの会という小さい親しいグループを作っていて、集まるたびに寄せ書の手紙をロランその人に送っていた。ヴィルドラックは、それ故、言わばロランの友情の使節として私たちには会いに来たのだった。私の家の畠の中での茶菓の集い、多摩河原の料亭や日本橋のソーダファウンテンでの晩餐会。『見つけもの』や『商船テナシテイ』の作者はアベイ詩人の真骨頂と、自由な人間の男々しさ、温かさ、慕わしさの感銘を、われわれの胸底深く刻みつけて帰国した。そしてその置土産は、われわれに本国の彼の友、アルコス、デュアメル、バザルジェット、マルティネ、ジャン・リシャール・ブロックらを知らしめて、その人々との友交の道を開いてくれた事だった。
私がドイツ語の勉強をはじめたのも此処での事だった。片山からヘルマン・ヘッセの話を聴いたり彼の手になるその詩の翻訳を見せられたりして、私はこのドイツの詩人のリリークの精神に深い親近感を覚えた。彼が第一次大戦中に書いた「平和」や「戦場での死」は、私の心を照らす全く新しい光だった。そのヘッセを原語で読みたいために志したドイツ語の勉強だったのである。まず片山から一冊の詩集を借り、近くに住んでいた友人で上智大学を出た中村吉雄に発音や文法の手ほどきをして貰った。真剣な意欲からのせいか進歩も早く、一年後にはたどたどしいながら『迂路』の中のやさしい詩ならば読めるようになった。ヘッセを思いドイツ語を思う時、私は若い日のこの二人の友人に心からの感謝を抱かざるを得ない。
本としては十三年六月に第二詩集『高層雲の下』が新詩壇社から、昭和二年五月にロマン・ロランの革命劇の序曲『花の復活祭』の訳が叢文閣から、同年九月第三詩集『曠野の火』が素人社から、更に三年三月訳書『ヴィルドラック選詩集』が詩集社からそれぞれ出た。
長男をうしなった年の昭和二年十一月父の死に会う。享年七十六歳。私たち夫婦にみとられて極めて安楽な臨終だった。昭和三年三月改めて実家に入籍して家督相統。同時に思い出多い高井戸を後にして東京市京橋区新川の実家に移った。母はやがて目黒に別居。
昭和三年四月〜六年(三十六歳〜三十九歳)1928年〜1931年
酒問屋に囲まれた新川の家では、今までのような自然の中での生活は全く不可能だった。自分の育った土地でありながら他郷に住む心地がして、後にして来た武蔵野の田舎がしきりに思われた。かてて加えて高井戸時代の親しい友人たちも、場所が東京も下町とあってはおのずと足が遠くなり、それと入れかわりに同じ詩人でも全然質や傾向を異にした人達が殺到するようになった。中には酒を目的の者、露骨に「略奪」や「たかり」を公言する者さえあった。私たち夫婦は憂欝になり、母の別居も一つはそれが原因だった。そしてたまたま訪ねて来る旧友も、以前と違った同席者を見たり、家庭内の何となく変った空気を感じたりして、私たちにもそれとわかる気まずい思いをして帰るのだった。
こういう時期にはからずも未知の登山家河田禎氏の『一日二日山の族』や『静かなる山の旅』を読んで感銘をうけ、やがてその人と相知るに至ったのは天恵だった。私は彼に案内されて遠近の山へ行くようになり、その紹介で「霧の旅会」という登山団体の会員にもなった。失った武蔵野の代りに山岳という一層広大な世界を得、私の詩に文章に山がその実体と雰囲気とを提供した。登山によって救われた私はそこに精神のための新しい支柱を見出し、自然への愛と傾倒とを一層深くした。それと同時に招かれざる客の数はしだいに減って、親しい旧友のほかに山の友達が新たにできた。読書の中に山の本が加わり、新しい熱情として自然地理学や気象学の勉強がはじまった。
しかし本来の仕事は文学であり詩であった。三冊の詩集は公けにしたものの、自分の詩への不満や、それの行きづまっている事は私も十分感じていた。そこへ或る日、茅野蕭々訳の『リルケ詩抄』というのが手に入った。それは真に驚くべき天啓だった。馴れない眼には一種奇異な使い方に感じられる日本語が、ふしぎな的確さと新鮮な美とをもって作者本人のいわゆる物を造形していた。一筋縄ではゆかず、到るところに抵抗があり、痛ましいほどの肉化があり、高次の羃(べき)があり、これを解く事ができたとき初めて一篇の滋味や魅力がわかるという種類の詩だった。私は眼が洗われたような気がし、いつかは自分の詩にもその影響の現われる日のある事を信じた。
六年十二月、この新川の家を買いたいという人の出たのを幸い、然るべき値段で売って、勇躍杉並区荻窪一丁目の新築の借家へ移った。
昭和七年〜一〇年(四十歳〜四十三歳)1932年〜1935年
再びの郊外住まい。旧居の高井戸にも近く、家のまわりに樹木も多く、少し出歩けば農家も畠も田圃もあった。仕事のほかに新しく始めたい事がぞくぞくと現われた。それを、こんな事の好きな妻に手伝わせてみんなした。山から採って来た花の栽培、附近の自然観察や昆虫と植物の標本作り、一日三回の気象観測と雲の撮影……九段の小学校へ通っている長女の栄子も母親を見様見真似に手を出した。家をからっぽにして散歩をしたり、日帰りの山登りを試みたり、妻も子供ものびのびとした生活を楽しんだ。その問にも私は山や高原の旅をし、詩を書き、文章を書き、なお合間には翻訳をして、一日といえども倦むことがなかった。八年六月には詩集『旅と滞在』が、十年七月には最初の散文集『山の絵本』が、いずれも山の書肆朋文堂から出版された。
昭和一一年〜二〇年八月(四十四歳〜五十三歳)1936年〜1945年
杉並区井荻の東京女子大学と善福寺池の近くに洋館建ての家を持って住んでいた友人の中西悟堂氏が、都合でその家を貸したいから居抜きのままで是非私に借りて住んでくれという話を持って来た。環境も家も荻窪のものよりも遙かに良いので、快諾して其処へ移った。大きな禽舎が有って小鳥を飼うことができ、広々とした書斎が明るくて立派だった。
この家には五年間住んだが、仕事の上にも成果があり、自然の観察や理科関係の勉強の上でも進歩があった。十二年にはミール・ジャヴエルの『一登山家の思い出』が、十五年にはジョルジュ・デュアメルの『北方の歌』と私自身の詩集『行人の歌』が、十六年三月と六月にはやはりデュアメルの『阿蘭陀組曲』と『モスコウの旅』とがいずれも竜星閣から出、十三年に散文集『雲と草原』、十四年にドイツ語からの私の最初の翻訳であるヘルマン・ヘッセの『ワンデルング』が、それぞれ朋文堂の手で出版された。
十五年秋、家の根継ぎをしたいという中西氏の申し出でを容れて程近い借家へ転居。
しかし一方ヨーロッパでは前年九月に第二次大戦が勃発し、我が国に対するアメリカ・イギリスなどの国際感情も引き続く支那事変以来いよいよ悪化と緊迫の度を加えて来た。そして六月にはドイツに対するフランスの降服が報ぜられ、九月には日独伊三国同盟が成立し、近衛内閣のもとに大政翼賛会が発足したり臨時中央協力会議が開かれるなど、われわれ一般国民には知る事もできず又知らされもしない政治上・軍事上の大なだれに巻きこまれながら、十六年十二月八日、ついにアメリカ・イギリスに対する天皇の宣戦布告を聴いた。ここに至るまでの事の真相に一切無知の私は愚かにも単純に国難を信じた。前線で尽すことのできない国民の義務を、後方で一致結束している同胞と共に果たそうと思った。そして求められればいわゆる愛国詩も書き、請われれば隣組長にも防空群長にもなって働き、要請をうければ講演の旅にも出た。しかし決して憎悪を煽っておのれのペンや口を汚した事はなく、ひたすら此の戦いに同胞すべての清からんことを熱願した。そして心中ひそかに死を覚悟していた。
十九年三月赤坂区青山南町六丁目に転居。ここでも請われて防火群長となる。長女栄子東京女子大学を中途退学して石黒忠篤の三男予備海軍中尉石黒光三と結婚。
二十年五月空襲によって家を焼亡。府下北多摩郡砂川村の親戚尾崎梅太郎方に寄寓。八月十五日降服、終戦。
戦争中に出版された自著。昭和十七年、ヘッセ詩画集『画家の詩』(三笠限定版クラブ)、写真と天気の解説『雲』(アルス)、散文集『詩人の風土』(三笠書房)、詩集『高原詩抄』(青木書店)、詩集『此の糧』(二見書房)、昭和十八年、詩集『二十年の歌』(三笠書房)、昭和十九年、詩集『同胞と共にあり』(二見書房)
昭和二〇年一〇月〜二一年八月(五十三歳〜五十四歳)1945年〜1946年
この間、千葉県三里塚附近に住む妻の実父水野葉舟氏方、東京府下吉祥寺の河田禎氏方、東京市杉並区中通町の井上康文氏方に順次転々と寄寓。二十年十一月、母しげ鎌倉大町名越の親戚原島宅で死去。享年八十三歳。
昭和二一年九月〜二七年(五十四歳〜六十歳)1946年〜1952年
元伯爵渡辺昭氏の厚意で、長野県諏訪郡富士見村に在るその別荘の一部を借り、高原の広大な自然美と土地の人々の愛情とに引かれるまま遂に七年をここで暮らす。
二十七年、東京都世田谷区玉川上野毛に家を新築し、十一月、思い出多い富士見を後に帰京する。
戦後及び富士見時代に出版された自著。昭和二十一年、散文の小冊子『麦刈の月』(生活社)、改訂増補『ヴィルドラック選詩集』(寺本書房)、選詩集『夏雲』(青園荘)、マーテルリンクの自然エッセイ集『悦ばしき時』(富岳本社)、昭和二十三年、選詩集『残花抄』(札幌玄文社)、散文集『高原暦日』(あしかび書房)、散文集『美しき視野』(友文社)、ロマン・ロラン『花の復活祭』(あしかび書房)、昭和二十六年、文庫版『山の絵本』(角川書店)、書き下ろし文庫版『碧い遠方』(角川書店)、昭和二十七年、文庫版『尾崎喜八詩集』(創元社)
昭和二八年〜三四年(六十一歳〜六十七歳)1953年〜1959年
多摩川の流れを見おろし、西南西に富士を望む丘陵上の家に妻、石黒光三夫妻、美砂子、敦彦という二人の孫たちと一緒に住んで、老来なお仕事もでき、富士見在住時代からの胃潰瘍も全治して健康も上々、おりおりは登山も試みる程である。そして昭和三十四年九月の現在、この恥多き略年譜に一応の終止符を打とうとしている。
帰京後に出版された自著。昭和二十七年、文庫版エミール・ジャヴェルの『一登山家の思い出』(角川書店)、二十八年、文庫版デュアメル『和蘭陀組曲と北方の歌』(角川書店)、デュアメル『わが庭の寓話』(創元社)、文庫版『尾崎喜八詩集』(新潮社)、文庫版『雲と草原』(角川書店)、二十九年、ヘッセ『さすらいの記・童話』(三笠書房)、三十年、詩集『花咲ける孤独』(三笠書房)、『新訳ヘッセ詩集』(三笠書房)、散文選集『わが詩の流域』(三笠書房)、『リルケ詩集』(角川書店)、三十一年、散文選集『山の詩帖』(朋文堂)、三十二年、改訂全訳ヘッセ『ワンデルング』(朋文堂)、文庫版『山の絵本』(新潮社)、三十三年、全集版増補『ヘッセ詩集』(三笠書房)、詩集『歳月の歌』(朋文堂)、三十四年、全訳リルケ『時祷詩集』(弥生書房)、『尾崎喜八詩文集』全七巻(創文社)。
---------------------------------------------------
●以下は、サイト管理人による補筆です。
昭和三七年(七〇歳) 1962年
『尾崎喜八詩文集』第八巻(創文社)出版。
古希を祝う会(学士会館)。
昭和三八年(七一歳) 1963年
デュアメル『慰めの音楽』(白水社)出版。
昭和三九年(七二歳) 1964年
散文集『さまざまの泉』(白水社)出版。
昭和四一年(七四歳) 1966年
詩集『田舎のモーツァルト』(創文社)出版。
上野毛から鎌倉市山ノ内に転居。
昭和四二年(七五歳) 1967年
散文集『私の衆讃歌』(創文社)出版。
初期膀胱腫瘍手術。
紫綬褒章受章。
昭和四三年(七六歳) 1968年
連載『音楽と求道』(芸術新潮)開始(昭和四七年一二月まで)
昭和四四年(七七歳) 1969年
散文集『夕べの旋律』(創文社)、『自註富士見高原』(青峨書房)出版。
昭和四五年(七八歳) 1970年
詩集『その空の下で』(創文社)出版。
昭和四六年(七九歳) 1971年
『素顔の鎌倉(共著:大佛次郎編)』(実業之日本社)出版。
昭和四七年(八〇歳) 1972年
散文集『晩き木の実』(創文社)出版。
昭和四八年(八一歳) 1973年
『音楽への愛と感謝』(新潮社)出版。(上記、連載「音楽と求道」を改題したもの)
潰瘍再発により、入退院を繰り返す。
昭和四九年(八二歳) 1974年
二月四日一二時四五分死去。
二月十日葬儀告別式(信濃町千日谷会堂/葬儀委員長:草野心平、司式:串田孫一)
|