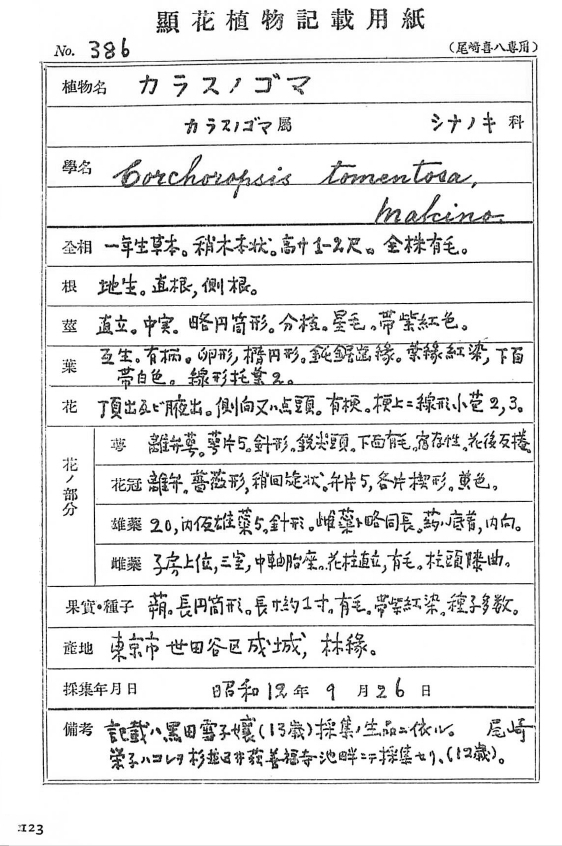夜明け前に爽やかな驟雨があったらしく、松本平の空の中ほどには、雨雲の名残りがいくつか、泉水をおよぐ鯉の群のように浮かんでいる。その背景をなす山々の関係的な高度から推して、乱雲というものの高さの観念がほぼ明瞭になる。驟雨のあとの五月の朝、彼ら空の種族は、この盆地の人生に一層親しく繋がっているように見える。そしてそれを列車の窓から眺めている私の方が、かえって偶然の他国者よそものたる身分をはっきりと意識させられる。
午前六時いくらという早い時間に、かくも多くの通学の女生徒を見るのは何の故だろう。項うなじの左右で振分けて結んだ短い髪、制服のジャンパア。妙齢というには未だ間のある、むしろ青い桃の実のように固い、健康な少女の野性の香を臆面もなく車内にまきちらしながら、いずれも膝の上に教科書や筆記帳をひろげて、地理、博物、英語、数学などの学科を、賑かに暗誦したり黙々と復習したりしている。おもうにこの子たちは今日試験を持っているのである。それで学校のはじまる前、なお一時間なにがしの試験勉強をかせぎ出すために、申し合せたように早出して来たのであろう。
右手の窓には朝日にけぶる雲の金髪をもやもやさせた美ガ原熔岩台地、左の窓にはおびただしい残雪を朝暾ちようどんに染めた北アルプスの連峯とその前山、そして雨後の田園を疾走する車の中では、四拍子の轣轆れきろくを圧してこれら制服の信濃乙女の朝の連禱リタニー……
午前七時、しっとりと湿った松本駅の前の広場、私を乗せた入山辺行の始発バスの運転手台に、若い女車掌が今朝切りたてのヒヤシンスを挿した。一本は紫、もう一本は珊瑚いろ。この山の都会の朝の空気にふさわしく清純で、陶器のような冷めたさを持った美しい花である。
同時にそれは、今日彼らの美ガ原をたった一人で訪れる私へのもっとも優しい春の朝の挨拶でもあった。
バスは町なかを目まぐるしいくらい幾度も直角に曲って地図と実景とを対照している私をまごつかせながら、やがて市の東の郊外へ出た。薄川すすきがわ流域の田園を紅にいろどるレンゲソウ、遠近のみずみずしい新緑。もう営巣を始めたツバメやイワツバメが、頻りなしに道路の上を翻ったり人家の軒下へ流れ込んだりする。
市中の小学校へ通う田舎の子供の群に幾つも出会う。彼らのうちで詰襟の洋服を着ている者は、そのズボンが大人のように長い。これは寒気の強い信州の田舎では常にみるところだが、その服がいつもひどく古びて垢じみているので、何となく小さい工場労働者のように見えるのも是非がない。かつてシュヴァルツヴァルト地方の風俗写真を見たことがある。その中でハスラハという町の小学生たちがやはり半ズボンならぬ長ズボンを穿いて、鍔の広いフェルト帽をかぶり、カラアに蝶ネクタイ、蝙蝠傘を小脇にかかえたいでたちが、まるで小さい田舎紳士であった。それはいいが足はおおむね跣はだしで、むきだしの踝くるぶしが哀れであった。しかしここではさすがに跣ということはなく、ともかくも一度は運動靴であったと云うことのできる一種の履物を履いている。
山が左右から迫って来る。打開けた田園がだんだん先ぼそりになる。川の右岸を行く道が次第に高くなる。袴越と出峰山との間、ちらほらと山桜の白い薄川の谷奥に、王ガ鼻から茶臼へつづく高原南端の雄大な懸崖が、星を鍛える巨大な鉄砧かなとこの縁かとばかり、大空を横一文字にかぎっている。
大手橋で下車。松本から二十五分である。深い沢の落口にかかった橋の袂で身支度をととのえる。崖には一面にしだれ咲く山吹の花、路傍には白いオドリコソウ。運転手は私が与えた一本の金口を大切そうにポケットヘ収めて、代りに常用のバットに火をつけた。車掌は腰に両手をあてて新緑の山に見入りながら、春や風景についていくらか詩的なことを彼に言う。そして運転手は「うん、うん」とうなずきながら、長閑に煙草をふかしている。
眼の前に立つ二三本のサワグルミ。若葉と一緒に伸びたその薄黄いろの■荑花しゅういかを今日の山路の最初の合図として喜びながら、やがて自動車の彼らと別れる。 [編者註:■は"茅"の下に"木"を添えた字]
バスは一声高く笛を鳴らして元来た道を帰って行く。私は橋をわたって反対に坂道をのぼる。朝の歩き出しの靴の軽さ。そよ吹く風の無言歌のような深さ、柔かさ。心はおもむろに所有の歌に満たされる。
麗らかな日光を斜めに浴びた三反田、部落の広場に「中入堰趾」と書いた標柱が立っている。道が二叉に岐れる。正面のものを入山辺・扉鉱泉への道と推測して、左へ敷石道をあがって行く。
ふりかえれば松本平にただよう霞の上に春まだ浅い雪の常念、蝶ガ岳。前景の農家の屋根で黄鶺鴒がチリチリ鳴いている。其処に立つ一本の山桜は山村の五月柱メイポウルと云っていい。あまりに美しい春を一人行く心よ! 私は行を共にして敢えて悔いざる友の名を指折り思う……
村を出はずれると漸く山道らしくなった。ホウムスパンの上着がいかにも暑い。脱いでルックサックヘ押し込んで、シャツとチョッキで行く。片側を細い水がちょろちょろ流れているが木立は無い。ひたすらに三城牧場の涼しい樹蔭が慕われる。
山の畠へ仕事に行くのだろうか、飲み水を詰めた一升壜を下げて鍬をかついだ女が行く。四つか五つになる女の児が、遅れ勝ちによちよちしながら付いて行く。何か知らぬが路端のいろいろな細かい物が彼女の注意を引くらしく、時々しゃがみこんで指先でほじったり調べたりして、道草を食っては先へ行く母親に呼ばれている。
自分も食べていたのでその子にネーヴルを一つ遣る。初めはびっくりして泣出しそうであったが、別に害意も無いと分るや、小さく両手の平をくぼませてその果物をうけとった。母親の知らぬ間の、二人だけの秘密の交渉である。
それにしても南北を山にふさがれた道のこの蒸れるような暑さ! 鶯が無数に鳴いている。蟬の斉唱は炎熱の夏の凱歌だが、余りに多い鶯の歌は晩春の温気をいやが上にも重たくする。
沢が二つに分れる。正面の沢の奥には、青ぞらを抜いて、大洋航海船の高い舳へさきのような王ガ鼻の一角がそばだっている。武石への山道がほそぼそと左の切畑へ消えて行く。五月の日射は其処に溜まり、自然は森閑、せせらぐ水に近く木を連びだす男が二三人、春の日永をのんびり働いている。傍には老人が一人、横たわった材木に腰をかけて煙草を吸いながら、仕事をする連中と何かぽつりぽつり話している。
あれから半道あまり進んだ。落葉松からまつの植林に沿って行く蔭の多い道だった。今やそのつぶつぶの新芽を綻ばせた落葉松は、淡褐色の枝に緑の霧を吹きつけたように見える。
林間疎開地をおもわせる打開けたところ、王ガ鼻と三城牧場への分岐路を示す標柱。石切場が近いか、あたりに散乱する石の破片、腰を下すとその温ぬくみの伝わって来る日に晒された熱い岩。たえず眼の前を飛び廻りながら、時々じっと眩ゆい路上に翼をやすめる孔雀蝶。ステッキに捕蟲網を取りつけて二羽を捕獲する。
松本の入らしい登山者が二人、足早に通り抜けて王ガ鼻への道を行った。私はゆっくり遊んでから、右へ、三城牧場への道をとった。道はすぐに登りになる。この尾根ひとつで牧場へ入ることができるらしい。途中、右手に谷がひらけて、落葉松の梢の上に残雪の北アルプスが美しかった。カメラを出してその眺めを撮影していると、また一人、今度は大きなルックサックを背負った若い人が登って来て、挨拶しながら通り過ぎた。
顔にながれる汗を拭きふき登って行く。やがて尾根通りへ出る。左へすこし登ると峠のような草原の小平地、木立が涼しい蔭をつくっている。其処へ行って涼みながら一息入れようと思ったらもう先客が一人いた。今しがた遭った大きいルックサックの人だった。挨拶をして草の上へ腰をおろす。
ここは南の眺望が晴れやかに開けて、自然が、壮大というよりもむしろその愛らしい一面を見せている。眼の前には熔岩丘のような観峰の大きなかたまりが浅緑に萌えて風景の中心になり、その下には大門沢の水の流れる草原がのびのびと拡がっている。そして観峰のうしろを、鉢伏、宮入とつづく美しい平頂の丘陵がぐるりとめぐって、この風景の牧歌的な性格にますます有力な寄与をなしている。夜上りの今日の快晴がさかんな上昇気流をつくっているのか、諏訪盆地の方角の空には、ぽかりぽかりと気球のような積雲の浮游。その雲の白さ、空の青さ、柔かな山々の線と地膚の色のあたたかさ。ぼんやり眺めて時の移るのも忘れそうだ。
私と並んでこの風景に眼を憩わせ心を遊ばせている青年は、松本の家具屋さんでM君といった。今日はお天気がいいから穂刈三寿雄さんの組立カメラを借りて来て、これから牧場と美ガ原とを写しに行くのだと云う。それでは丁度いいから一緒に行きましょうということになって腰を上げた。
佳いお天気と、穂刈さんの組立カメラと、春の山。私にとってはそれだけで充分詩だった。「これがその写真機です」と云いながら、M君は横ひろがりに嵩ばったルックサックを撫でて見せた。
これまでに幾度か人の書いたもので読みながら、さまざまに想像していた三城牧場。これがあれか? なるほどと思えば思えるし、違うと云えば云えもする。読むことがむずかしいように、書くこともまたむずかしいものだと思った。
牧柵を越えて中へ入ると、大きな岩の散乱するあたりに一本の棠梨ずみらしい老木がある。未だ花は咲いていないが、四方へ張った大枝小枝が地面の上へ複雑な影を落としている。先ず其処へ行ってルックサックを下ろして、何はともあれ撮影にとりかかる。
M君はと見れば、彼もまた向うで早速始めていた。三方へ踏んばった木製の大三脚が機関銃の台座のように見える。
最初放牧の牛が六七頭いたが、私たちが入り込んで来るのを見るやのそりと立ち上って歩き出し、今では二頭になってしまった。この二頭にまで逃げ出されてはどうも牧場の絵にはなりにくかろうと、それで直ぐに用意に掛った訳だった。
正面奥にはあの百曲りの急坂を見せた美ガ原南東の懸崖、つづいて右に茶臼山西尾根の厖大な一角、中景は丘陵性の台地の起伏と落葉松林、前景には散乱する安山岩の自然の布置と二頭の牛。これが私の構図だった。
ともかくもこうして撮影を済ますと、パイプを啣くわえて私はこの牧場をもう一度見直した。
これは三方を馬蹄型に山でかこまれた谷合緩斜地の牧場である。その中を薄川の一支流が二本の沢となって貫流して、この両者の間を落葉松や躑躅の類の密生した氷河堆石のような丘陵状の尾根が走っている。それがため全景は長軸の方向に沿って幾つかに分たれて、牧場そのものの印象は、一見ひどく奥まった、細長い且つ狭いものに見える。
東信牧場や蓼科牧場はむしろ凸面の牧場の美に属するが、この三城牧場の良さは正に凹面の牧場のそれだと云える。彼処で遠山の翠微が牛たちの円つぶらな瞳にうつるとすれば、此処では暮靄の底に彼らの夕べの声が消え入るであろう!
むこうでは小屋が真昼の薄青い煙を上げている。時計を見ると十二時に近い。私は小さい流れで手を洗うと、今やスイスの何処かのアルプヘでも来た気になって、弁当をつかうためにその小屋の方へ大股に歩いて行った。
私のように小屋へ入り込んでお茶などは貰わずに、美しい風景を眼の前に水で弁当をつかったらしいM君が、向うの路のへりへ腰をかけてちゃんと私を待っている。たとえ偶然の道連れとはいえ、美ガ原まで一緒にと契ったものを、なぜ外で肩を並べて食おうとしなかったのであろう。どうして其処へ気が付かなかったのだろう。およそこんな心遣いを、人間極めて当然なこととして、常々幼い者などにも言い聞かせている自分なのに。
私は恥じた。同時に、その人に対して、今までよりも一層の関心を持つようになった。
私たちは小屋の横手のちょっとした高みを越え、沢を下りて水を渡り、向側の丘陵を横断して百曲りの方へ進んで行った。
山の牧場というものは離れて見た眼には歩くに楽しい草原として映るが、さて実際にその場に足を踏み入れてみると案外歩きづらいものである。ふっくらした面、のびやかな線の流れのように見えたものが思いの外でこぼこで、その上何か非常に大きな海綿でも踏んで行くように足に確かな応えが無いために、長くつづけば膝頭ががくがくしてくる。
私たちの横断した緩やかな丘陵がやはりその例に洩れなかった。それはまるでかさかさに乾いた浮洲だった。かてて加えて真昼間の太陽は苦しいまでにいきれを立たせ、灰のような軽い土は靴を覆って、汗ばんだ手の甲にまで真黒にこびりついた。
しかしもう後一週間たった頃の美しさをどんなだろうと想わせる蓮華躑躅はこの牧場に一面だった。また暑さと苦しさとに対する報償として、清らかな声で鳴く小鳥もあった。その上私にとっての最大の仕合せは、求めても容易には得難いような、実に一箇の「見つけ物デクウヴェルト」とも言い得るような、実意に満ちた、感じばやい、優しい心の道連れを偶然にも持ったことだった。もしもこの人との遭遇がなかったならば、私はこの暑さと、この歩行の苦しさとに辞易して、或いは牧場小屋に泊ることの易きについたかも知れなかったのである。
遂に苦しみが去って楽しみが来た。
不安定なぽか土が終って確乎とした岩の道が始まった。
沢が現れ、水が潺湲せんかんと流れている。岸の岩の間には到るところコキンバイの花が黄金いろに咲き、日光に照りかがやき、跳ね躍る水のいきおいに顫えている。
私たちは当然のことのように静かに其処ヘルックサックを下ろした。そしてお互いに少しやつれの見える和やかな顔を見合せた。この瞬間「友」という言葉がこの若い道連れに対する実にはっきりした観念となって私を襲った。私はその言葉を咀嚼してみた。間違ってはいなかった。齟齬するものは何ひとつ無かった。その友は膝の上へ両手の指を組合せて、練絹のように捩れて伸びる水の流れを身うごきもせず見つめている。
私は黄金いろに花咲くコキンバイの二株三株を家苞いえづととして採集した。すると友は何時の間にか腰を上げて、私の採ったよりももっと立派なのを採って来て呉れた。彼はまた一種の董も探し出して呉れた。それは私の全く知らない種類だった。
沢を過ぎれば今度は小さい草原だった。一つの楽しみの後へまた別の楽しみが続くのだ。花の次には蝶だった。
私は其処でギフチョウの飛んでいるのを見た。ギフチョウは六年ばかり前に石老山でたった二羽を採集したきりである。しかもそれは鱗粉もはげて哀れな姿のものだった。ところが今見たギフチョウは、飛んでいてさえ黒と黄との色彩を鮮明に識別することができるほどに新らしい。私の胸は躍った。私はすぐさま捕蟲網を取り出した。そして散々追廻した末にとうとう捕えた。しかも私の喜びを狂喜にまで押上げるかのように、手の内のそれは紛れもないヒメギフチョウだった。ヒメギフチョウは私にとっては初めてである。
この活劇を見ているうちにM君もたまらなくなったらしく、私から網を受けとると一羽のキベリタテハを追いはじめた。しかし蝶の狩猟にも幾らかのこつはあると見えて、かつて八ガ岳で私の義弟を散々なやましたキベリタテハは、私のこの新らしい初心者の手ごつちには終えなかった。
M君はとうとう断念した。
「どうもむずかしいものですな」
そう云いながら彼は私に網を渡した。
右は陣ガ坂、左は百曲りへの分岐点だった。
こんな道草を食いながら、いったい今を何時だと思う。午後一時半を過ぎている。そしてお前は美ガ原から抑も何処へ行こうと云うのだ。上和田へ。
しかも私は百曲りの登りがどんなに苦しいか、また美ガ原から上和田への道がどれほど長いか、みんな本で読んで知っている。ただ知らないのは自分の実地の体験だ。
私は心中でこんな問答をした瞬間、冷水を浴びたように身ぶるいを感じた。
その百曲りが眼前に長い急坂を懸けている。頂上の熔岩の崖はまたその上で砦のように聳えている。しかも雲。北西の天から広々と流れ出しているのは米の磨水とぎみずのような巻層雲。ああ、急がなくてはならない! 行かなくては!
その急な長い登りを若い友の後から私は行く。諦めた人のように。追上げられる者のように。
百曲りは、謂わば美ガ原の熔岩がその節理にしたがって薄板のように剥落して作った崖錐面に、幾曲折の電光形を描いて付けられた登路だと言えよう。したがってそのガラガラの程度は上へ行くほど烈しく、樹木の生えているのは下から中腹あたりまでか、或いは上の方でも斜面が一部棚状を呈して、比較的地盤の安定が保たれている個所であるように見えた。
一曲り行つては息をつき、三曲り行っては振返ることに密かにきめてじりじり登つた。振返るたびに槍、穂高、乗鞍、御嶽などがせり上った。乗鞍頂上に拡がった雪の、氷河のように青白く光るのが妙に心を重くした。
時のたつにつれて巻層雲の領域はますます広範囲になって来た。太陽はその光が次第に水っぽくなって、痣あざのような色の傷ましい大きな暈をさした。
今朝牧場下の分れ道で見かけた王ガ鼻口からの二人の登山者が、身を翻して飛ぶように下山して行った。その身分が今はひどく羨ましかった。ああ降りの嬉しさよ! 私は不図今夜の和田の泊りを空想したが、それまでの前途を思うと忽ち心は暗くなった。
しかし何事にも終りは有るように、この辛い百曲りの登りもやがて終って、とうとう美ガ原の上へ私は立った。最後の曲りの処で一足先へ行つて貰った松本のM君は、原の奥の方を見に行ったのか、もう何処にも姿が無かった。
私は枯草の上へどっかりと坐り込んで一時間ぶりにパイプをくゆらした。突然瘧おこりが落ちたように、一時に重荷が下りたように、気も軽々、身は万遍なく自由自在になって、何だかひとりでに微笑まれた。
「来てよかったな! 来てよかったな!」
そんな言薬を心は歌に歌っていた。
それから疲れが恢復すると慌てて写真機を取出して、先ず原の西端の断崖を槍と穂高を入れて写し、次に一人で記念撮影をした。それが済むと今度は空身からみで歩き廻った。三時に会って別れましょうと、M君と約束したその三時まで。
M君からの最近のたより――
「先日は御転居の御通知を下さいまして誠に有難う御座いました。御無沙汰をいたして申しわけ御座いません。其後お変りもなくお暮しの事と存じます。下って私も変りなく暮しております故他事ながら御安心下さい。
松本も大変に暖くなってまいりました。憎い程の寒さからのがれて、又暖い春の日をむかえる今日此頃は、遠く忘れかけていた山々のことが想い浮べられます。古い写真機でも持出して行きたいような美しく晴れた日が毎日続きます。
アルプスの山の麓は雪がまばらですが、峯へ行くにつれて真白です。今日は曇って見えませんが、吹雪になっている事でしょう。美ガ原方面の山にも下の方にはもう雪がありませんが、峯には何処も雪があります。
こんな事を書いております間にも昨年の山中での思い出が浮んでまいります。其時に苦しかった事も、月日が立って思い出となった時は、ほんとうに楽しくも亦なつかしいものです。私共はいつも山を見なれているせいか、いつでも山へ行けるという考えでおりますものですから大して行きたいとも思っておりませんが、それでも、たまには登って見たいなあと思う時には、たまらなく山へのあこがれが体にみなぎって参ります。
山でも一日か二日がかりで行けるような緑の山が好きです。
皆様へよろしくお願いいたします。時節柄御身御大切になさるよう御願いいたします」
M君への返しに書斎での写真に添えて――
「懐かしいおたよりを嬉しく拝見しました。まためぐって来た清明の季節に、松本の自然を生返らせる早春の光や色や、さては活気づく人々の心のさま、さこそと遥かに推察されます。
自分の仕事そのものさえ、或る無形の威迫を受けているように思われたあの事件(註、二・二六事件)からの魂の悩み、心の動揺が漸く鎮まると、折からの転居を機会に、また新らしく盛返した信念にしたがって、前よりも一層確乎として毎日の仕事にいそしんでいます。
自然は僕にとっては自分の芸術の生みの母です。僕は母を尊敬し、愛し、この母に依り頼み、それに聴き、そして永遠の赤児のように彼女に縋って、その豊かな胸から絶えず飲みます。僕を人間たらしめる「人間の汁液」は、彼女の乳房からマナのように降りそそぎ、流れます。これこそ創造の尽きる時なき泉です。
そしてやがて死ぬべき者僕が、仕事を終えて、この世の緑の夏草の中、白い石の下に朽ちる時、不死の者、母なる自然は、その大いなる見えざる指で、宇宙をわたる微風の中に僕の小さな名を書くでしょう。そう信ずることのできた瞬間、僕はこの写真をとりました。あの美ガ原での無上の時間をあなたが思い出すその時々、あなたの記憶の映写幕エクランにこの一人の友の俤が浮んで来るよすがにもなれと念じながら、今これを御手もとに届けます」
約束の午後三時、私は美ガ原山上でM君と袖を分った。別れのための約束は却って再会の約束を生み、さらに写真の交換の、時々の消息の遣取りの約束を生んだ。また茲にほだしができた。しかしたまたま誰かと覊絆に結ばれることが、なんと私を人間らしくすることだろう!
私は高原の縁を陣ガ坂の方へ歩いて行った。三城牧場の小屋番に、此方を近いと教えられたからである。空は漠々と雲を増して、太陽の姿はみられなかった。北アルプスもただ俤のように見えて、光のない雪が悲しく白い。風がぼうぼうと吹きわたる。寒さが身にしみて来る。この広大な美ガ原をいま歩いているのは自分一人だという自覚が、或る誇らしい気持と同時に底知れぬ淋しさを私に抱かせた。
茶枯れた草と風との中に、何か真白な物が横たわっている。その白さは寒水石に似ている。近づいて見たら馬の骸骨だった。私は後をも見ずに足を早めた。
やがて茶臼山との鞍部の陣ガ坂。雲が薄れて弱々しい日が洩れて来た。正面にとおく聳える蓼科山から、その麓にひろがる一帯の高原。其処には赤々と夕日が流れて、今日の終焉を飾っている。「これだけはどうあっても」と、私は峠の下り口へ三脚を立てた。
陣ガ坂の降りがこんなに悪いとは予想だもしなかった。
初め下り口では事態が極めて良好だった。道幅は有るし、障害物もなく、足は降りを喜んで軽くすたすたと下って行った。ところがものの半町も行かないうちに、そろそろコメツガやウラジロモミの倒木が現れて、下へ行くにつれて数も次第に増して来た。それは急な坂道を通せん棒して、くぐるには枝が邪魔になり、跨ぐにしては太い上に高過ぎた。詮方なしに道の片側の小高い笹藪へもぐり込んで、其処で乗越えて、また道へ戻るのだった。しかしこんなことを幾十度と繰返しているうちに、とうとう太い倒木が縦に何十本か重なり合って沢をふさいでいる処へ出た。枝のない丸太ならばその上を歩いて行くという手段もある。人間の腕よりも太い枝を八方に仲ばした何丈というツガやモミが、元末もとすえごっちゃに幾本も重なっているのだから、猿ででもなければ渡れはしない。あたりは暗くなる。空は掻曇って時々パラパラと落として来る。せめて野々入まではどうあっても行かねばならないと、とうとう思いきって靴を脱ぎ、幹を渡り、大枝を跨ぎ越しながら、応接にいとまもないほど先へ先へと現れる倒木群を猿のように飛び移って、七八町の間を一時間あまり費し、漸くこの難関を脱したのだった。
私はへとへとに疲れた全身を道そのものの傾斜に任せて、落ちるように下りて行った。やがてかなり広い荒涼とした枯草の原へ出た。骨ばかりになった大きな小屋が一二軒立ち腐れていた。また西の方で雲切れがして、夕暮近い金色がかった上空の雲がこの一帯の荒野原に不思議な光を落としている。往手は物見石からの高い尾根でふさがっているように見える。地図によればその直下には野々入川が流れているわけだから、其処まで行けば普通登山者の通るあの木材運搬の木馬道きうまみちに出逢うだろう。そう思って元気を出して歩き出した。
その草原が終って道が落葉松林の中へ消えこもうとする頃、私は往手に大きな炭俵を二俵背負った一人の男の後姿を発見した。私は大声でその男を呼び止めた。彼は返事の代りに手を上げて合図をして、急ぎ足で行く私を待っていた。私は早速「ルックサックを添荷にしてくれないか」と交渉した。「二貫目ぐらいならば」と云って重味をひいて見て、「四貫はありますね」とちょっと真面目な難色を見せたが、やがて頷いて引受けた。私はほっとした。
「その俵はどのくらいあるの」と訊いたらば、
「一俵九貫です」と答えた。
「君の家は何処」と重ねて訊くと、和田の上の鍛冶足かじあしだということだった。それでは上和田との分岐点の野々入までと約束して、二人並んで歩き出した。
もう六時に近く、山の日は暮れて空だけが青く明るい。私たちは野々入川に沿って歩いていた。白樺の林がみずみずしく白く、若葉の色が夕暮はわけても冴える。ジュウイチが二三羽絶え入るように嗚いている。山の斜面のところどころに山桜がほのかに白く淋しくはあるが、何か胸迫るような悲しみを帯びた、美しい平和な春の夕べの山道である。
厭だと断れば断れるものを、私のために唯さえ重い荷の上へこの荷をつけた男に対して、私は感謝を交えた愛を感じる。あの寂寞たる草原で私のルックサックを引受けた時、それが決して儲けずくではなかったことを私は固く信じて疑わぬ者だ。彼の眼が、そして今はまた私にも聴こえる彼の呼吸のせわしさが充分それを物語っている。街道まで背負って行きましょうと云うので、私たちは野々入から鍛冶足への山道を越えたのである。
もう夜になった鍛冶足、下の方に電燈をちらちらさせた鍛冶足。その火ノ見櫓の下に彼の家はあるのだと云つた。
その坂道で、私は彼の手に無理に賃金外の感謝の印を握らせると、受取ったルックサックを引担いで街道をすたすたと、今宵上和田の宿、「翠川」を指して歩いて行った。
|